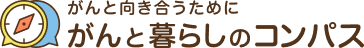がん治療に伴う口の中の痛み
Qがんの治療を始めてから口の中が痛いのはなぜですか?
粘膜のただれや潰瘍形成を伴う痛みであれば口腔粘膜炎(口内炎)、乾燥によるヒリヒリとした痛みであれば口腔乾燥、急に痛みが現れたのなら口腔感染症が考えられます。
- 抗がん剤や頭頸部の放射線療法
一般的に、抗がん剤は新陳代謝が活発な細胞に作用します。口の中の粘膜細胞はこれに相当するので、抗がん剤の影響を受けて口内炎ができやすくなり、痛みが生じます。唾液を作る細胞も薬剤や放射線の影響を受けやすく、その結果、唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥して痛みを感じることがあります。
また、頭頸部(脳と目を除く首から上のすべての領域)の放射線療法はがん細胞だけではなく、がんの周囲にある正常な細胞や組織にも影響を与え、口内炎や口腔乾燥などを引き起こします。 - 細菌感染
抗がん剤などによって免疫機能が低下し、抗菌作用のある唾液の分泌が減少すると、細菌感染によって炎症が起きやすくなり、痛みを感じることがあります。
?疾患の詳細説明
?口腔粘膜炎(口内炎)
抗がん剤治療や頭頸部の放射線療法など、がん治療に伴って生じる口内炎のことで、口の中の粘膜の発赤や腫れ、潰瘍、出血などが起きます。
口内炎は、がん治療により口の中の粘膜がダメージを受けることで生じます。口の中の副作用では比較的頻度が高く、抗がん剤の使用で30~40%、造血幹細胞移植(大量の抗がん剤使用)で70~90%、抗がん剤と頭頸部(脳と目を除く首から上のすべての領域)への放射線療法の併用でほぼ100%現れると報告されています。特に、免疫機能が低下していると粘膜の炎症で生じた傷に細菌が感染し、ときには全身の感染症に広がってしまうリスクもあるので注意が必要です。
抗がん剤による口内炎は、主に唇の裏側や頬の粘膜、舌の側面などの部位に生じることが多く、抗がん剤投与後5~7日目頃から発症し、10~12日目でピークをむかえ、3~4週間で軽快・治癒に向かいます。その他、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬では、口内炎が発生する部位や時期に違いがあります。頭頸部の放射線療法による口内炎は、放射線が照射されて影響を受けた粘膜に生じます。照射の回数を重ねるに従って悪化する傾向があります。治療が終了すると治癒しますが、時間がかかる場合があります。
閉じる
?口腔乾燥
がんの治療によって唾液を作る細胞がダメージを受けると、唾液の分泌量が低下して口腔乾燥が生じます。
唾液には抗菌作用があり、口の中の細菌の増殖を防いでいます。そのため、唾液が不足して口が乾くと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。原因としては、抗がん剤などの薬剤、頭頸部(脳と目を除く首から上のすべての領域)の放射線療法の副作用のほか、ストレスや口呼吸などがあります。
軽度の場合は、口の中のネバネバ感や乾燥による違和感があります。歯垢や粘膜表面の付着物が増加していくと、口臭も強くなります。重度になると、舌表面のひび割れなども生じ、痛みで食事や会話に支障をきたします。口腔乾燥の状態を放置すると、口の中に多種多数存在する常在菌のバランスが崩れ、口腔感染症が起きやすくなります。
閉じる
?口腔感染症
がん治療の副作用で免疫機能が低下し、細菌や真菌、ウイルスなどが増殖して口の中に感染症が起こることがあります。口の中の痛みが急に強くなった場合は、何らかの感染が起こっている可能性があります。
がん治療の内容により、免疫機能が低下する「骨髄抑制」という副作用が起こることがあります。このような状態のときには、口の中の常在菌による感染が生じやすくなります。治療の副作用による吐き気やだるさなどで、普段通りのセルフケアが難しくなるようなときは注意しましょう。細菌に限らず、カンジダやヘルペスウイルスなどによる感染症も起こることがあります。
虫歯や歯周炎など、歯や歯肉にかかわる感染症の治療を行わないままがん治療を始めると、骨髄抑制の状態のときには、今まで症状がなくても急に痛みや腫れが起こることがあります。口腔感染症は痛みで食事がしづらくなるだけでなく、ときには全身の感染症に広がってしまうリスクもあるので、治療前からのお口のチェックと適切なセルフケアが大変重要です。
閉じる