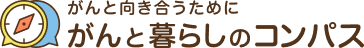味がしないときの工夫
Q味がしないときの工夫はありますか?
香りや出汁、温度などを工夫してみましょう。
出汁を利かせたり、ゴマや柚子などの香りや酢を使用したりすることで、食べやすくなります。また、できたての温かいものよりも、少し冷ました方がおいしく感じることがあります。
味覚障害の症状はさまざまなため、ご自身が食べやすいものを探してみましょう。
参考情報
- 1) 公益財団法人 がん研究振興財団:改訂版 がん治療と食生活 ~栄養士・看護師・歯科医からのヒント~
https://www.fpcr.or.jp/data_files/view/145/mode:inline
?疾患の詳細説明
?味覚障害
「甘味」、「塩味」、「酸味」、「苦味」などがわかりにくい(味覚鈍麻)、わからない(味覚消失)、異なる味に感じる(錯味)状態のことを味覚障害といいます。
味覚障害は、口の粘膜に存在する味を感じとる細胞(味蕾:みらい)が障害されたり、この細胞へ味物質が伝達されなかったりすることで生じます。加齢や薬剤によっても起こりますが、唾液の分泌量の低下、口の中の衛生状態の不良、神経系の異常、亜鉛の欠乏なども原因になります。特にがん治療においては、胃がんの手術、頭頸部(脳と目を除く首から上のすべての領域)の放射線療法、ある種の薬物療法で起こりやすくなります。薬物療法による味覚障害は一時的であることが多いですが、頭頸部の放射線療法では長期にわたって持続する場合も少なくありません。味覚障害は、食欲不振をまねき、栄養摂取量を減少させることにつながります。
閉じる