ワクチンで備える
暮らしを守ってきたワクチン
ワクチンによって、感染症の流行や重症化が大きく減った例がたくさんあります。
そんな“変化”を振り返りながら、ワクチンの種類やしくみもわかりやすくご紹介します。
ワクチンによって、感染症の流行や重症化が大きく減った例がたくさんあります。
そんな“変化”を振り返りながら、ワクチンの種類やしくみもわかりやすくご紹介します。
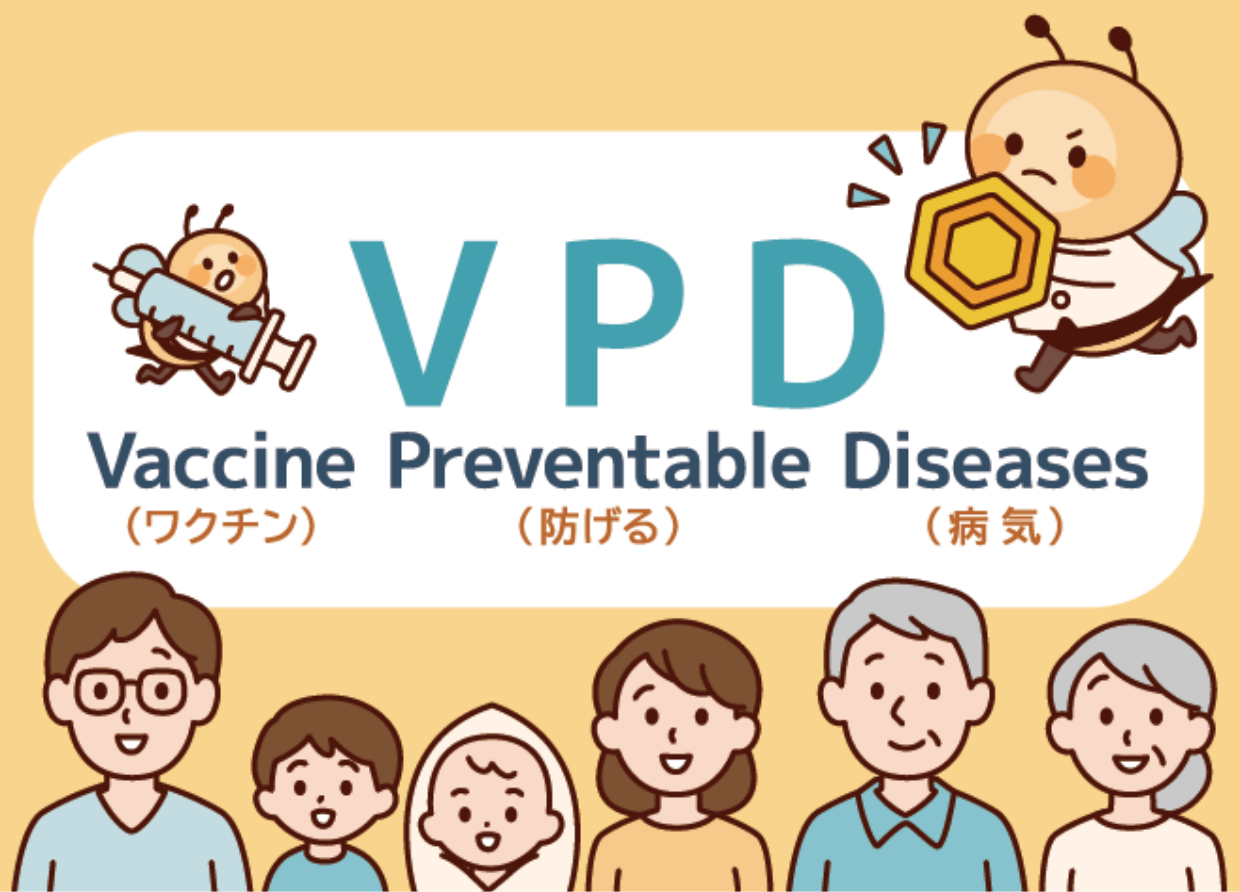
ワクチンによって、流行や重症化が大きく減った感染症はたくさんあります。
はしか(麻しん)
ワクチンが無かった頃は「子どものうちにかかるもの」とされていましたが、重症化しやすく、命にかかわることもある感染症です。
ワクチン導入前(1960年代)は毎年数十万人が発症し、年間500人以上の子どもが亡くなる年もありました。
現在はワクチン接種が進み、国内の患者数は激減。2015年には「日本は麻疹が排除された状態」と認定されましたが、近年は接種率の低下や海外からの持ち込みで再び流行のリスクが高まっています。
参考情報:国立感染症研究所「麻疹」
水ぼうそう(水痘)
水ぶくれが全身に広がる病気で、かゆみが強く、発熱や合併症も伴うことがあります。
ワクチン導入前(2014年以前)は、子どもがほぼ全員かかる「通過儀礼」のような病気で、毎年100万人以上が発症していました。大人がかかると、重症化や後遺症のリスクが高いという報告もあります。
2014年から定期接種が始まり、小児の患者数は激減。発症しても症状が軽くすむケースが多くなっています。
参考情報:国立感染症研究所「水痘」
B型肝炎
肝臓にウイルスが残り続ける「持続感染」になると、肝がんや肝硬変のリスクが高まります。
血液や体液を介して感染し、かつては知らないうちに感染しているケースも多数ありました。
現在は、乳児期の定期接種が始まり、感染のリスクは大きく減少しています。
参考情報:国立感染症研究所「B型肝炎」
破傷風(はしょうふう)
土や汚泥にいる破傷風菌が、けがをしたときなどに体に入り、全身の筋肉が硬直したり、呼吸ができなくなったりするとても重い感染症です。
ワクチン導入前(1950〜60年代)は年間500人以上の死亡例がありました。特に高齢者や出産直後の女性や新生児での発症が多くみられました。
現在は、二種混合(DT)、三種混合(DPT)、四種混合、五種混合ワクチンにも含まれており、子どもでの発症は非常にまれになりました。
ただし、破傷風ワクチン接種歴のない高齢者や、ブースター未接種で年長児や大人になってから免疫が落ちている者の発症例もあり、今でも注意が必要な病気です。
参考情報:国立感染症研究所「破傷風」
子宮頸がん(HPV)
ヒトパピローマウイルス(HPV)が原因で起こるがんの一種で、毎年約3,000人の女性が亡くなっています。
かつてワクチンの副反応への不安が広がりましたが、国内外での継続的な調査・研究をふまえて積極的勧奨は再開され、国内での接種率は回復傾向にあります。
以前から接種が進んでいる海外の国々では、ワクチン導入世代で前がん病変の頻度が非常に低下するなど、実際の予防効果も報告されてきています。
参考情報:厚生労働省「子宮頸がん予防の最前線」
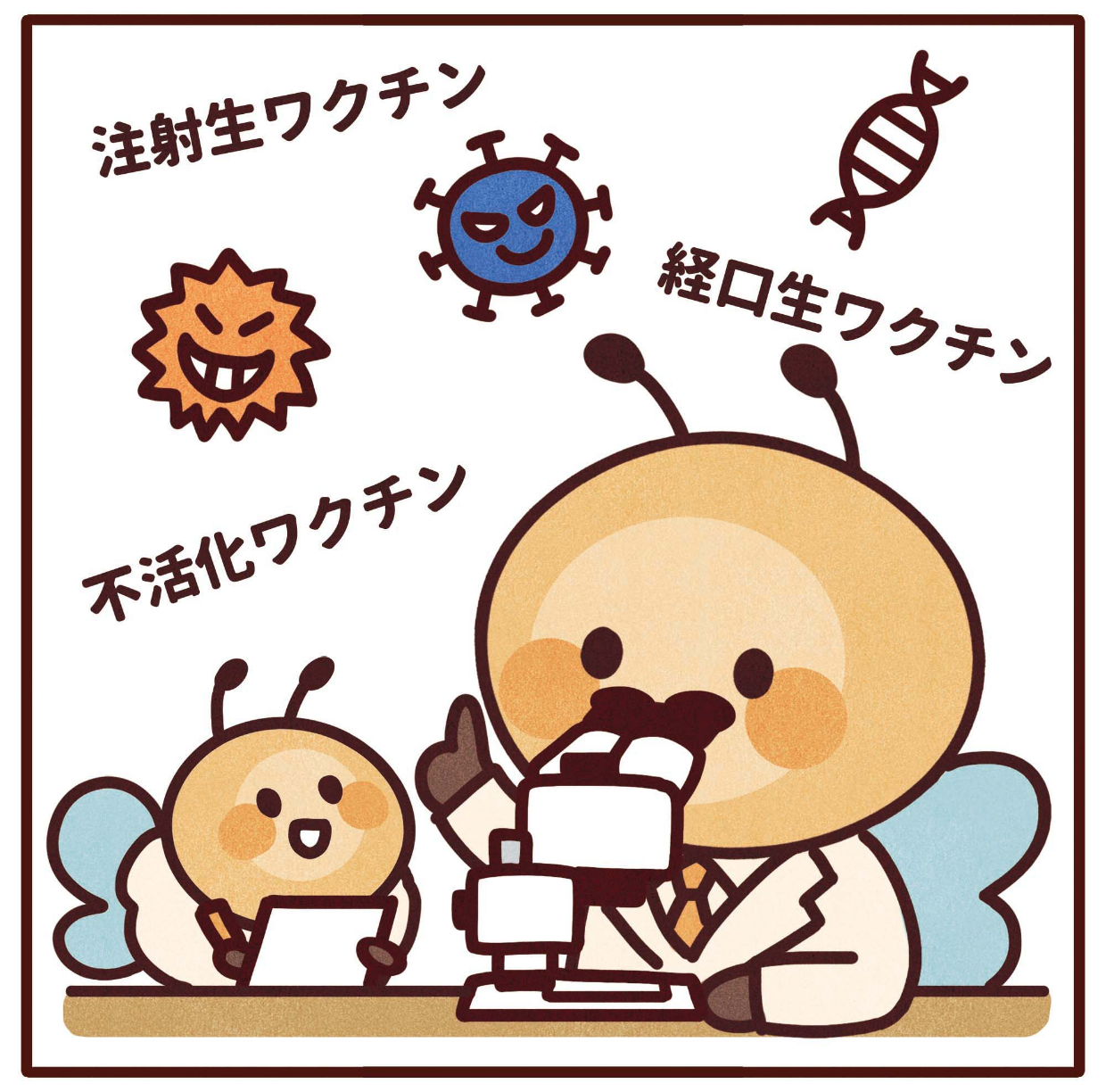
ワクチンにはいくつかのタイプ(つくり方や働き方)があり、それによって効果の出方や副反応の出やすさも少しずつ異なります。
ワクチンの種類をおおまかに知っておくことで、「このワクチンは1回で終わる?何回打つの?」「なぜこの時期に打つのか」といったことが少しずつ見えてきて、不安が「納得」に変わっていきます。
自分のためにも、家族のためにも、“よくわからないから不安”から、“ちょっと知っているから安心”へ。そんな一歩として、種類の違いに少しだけ触れてみましょう。
生ワクチン
ウイルスや細菌を弱らせて体に入れるタイプです。実際に体の中で少し増えて、免疫をつくります。
その病気に自然にかかった時と似通った免疫がつくのが特徴ですが、体調が悪いときや免疫が弱い人は受けられないこともあるため、その点については注意が必要です。
代表的なのは、BCG(結核)、麻しん・風しん、水ぼうそうなどです。
不活化ワクチン
病原体の
体の中では増えないので、ワクチンが原因でその病原体による病気にかかることはありません。ただし、しっかり免疫をつけるために複数回の接種が必要になることが多いです。
五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)や、注射するインフルエンザワクチンなどがこれにあたります。
mRNAワクチン
ウイルスそのものを入れるのではなく、ウイルスの一部の設計情報だけを体に届けて、免疫に覚えさせるという新しい仕組みのワクチンです。
ウイルスそのものは一切入っておらず、感染のリスクはありません。また、ワクチンが体に残り続けることもありません。
新しいワクチンを開発できるスピードが速く、将来の新たな感染症にも対応できる次世代型ワクチンとして注目されています。
次世代mRNAワクチン(レプリコン)
mRNAワクチンの技術をさらに進化させた「次世代mRNAワクチン」です。
通常のmRNAワクチンは、一度に体内へ届ける量がある程度必要ですが、レプリコンワクチンは体の中で一時的に情報を増幅できるため、少ない接種量でも免疫をつけることが期待されています。
出典:厚生労働省「予防接種・ワクチン情報」より当社作成
監修医師:中野 貴司 川崎医科大学 小児科学特任教授、日本小児科学会 小児科専門医・指導医、日本感染症学会 感染症専門医・指導医、ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター
/
— Meiji Seika ファルマ株式会社 (@Meiji_Seika_p) October 1, 2025
「#話そうワクチン」プロジェクト
新CMを本日よりTVやTVerで放映開始!
\
感染症から人々を守りたいと願う医師の姿と、当社が実施した調査結果を伝え、ワクチンについて医師との対話が生まれることを目指しています。 pic.twitter.com/BRpvvoyDh7