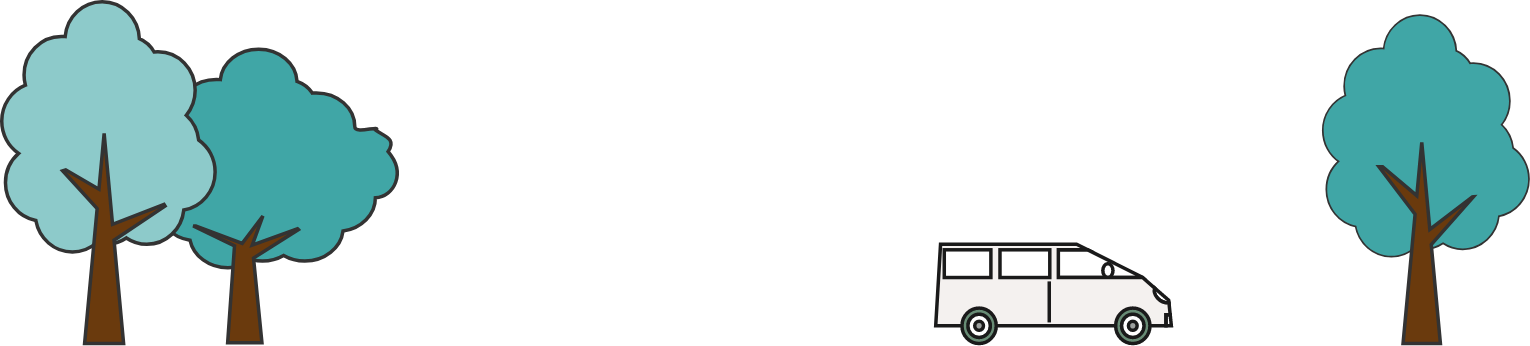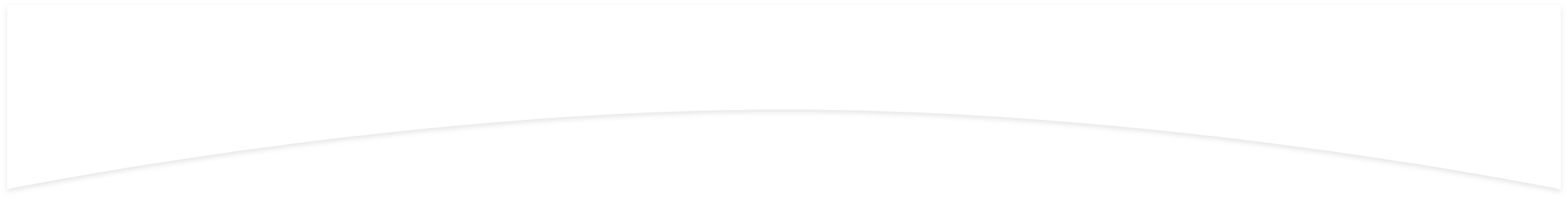

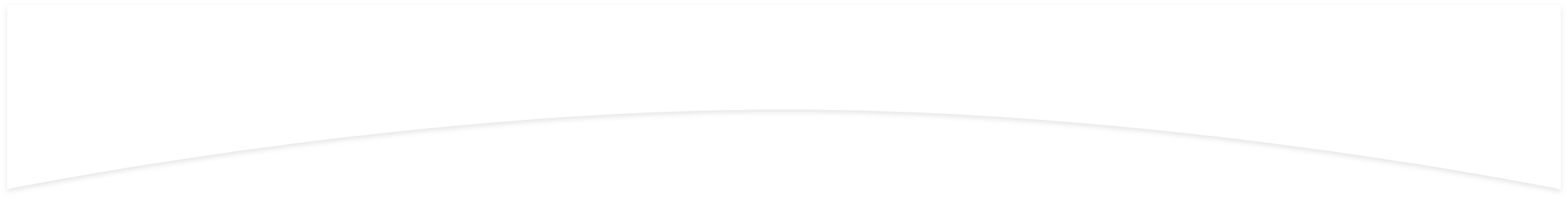

造血幹細胞移植に特有で注意が必要な合併症に、血栓性微小血管症(TMA)と肝中心静脈閉塞症/類洞閉塞症候群(VOD/SOS)があります。病態の解明と、診断方法や対策、治療方法が現在も進歩しつつあります。
血管の内側の細胞が傷つくことによって、血栓症などが引きおこされ、さまざまな臓器に障害があらわれます。移植前処置や免疫抑制薬、移植片対宿主病(GVHD)、ウイルス感染などがきっかけになると考えられています。一般的に、非血縁ドナーやHLA不適合ドナーからの移植で発症が多いとされています。
症状は、消化器障害(下痢、下血など)、意識障害、けいれん、呼吸困難、血小板減少、貧血、腎機能障害、肝機能障害などがあらわれます。
治療方法は免疫抑制薬の減量・中止が基本ですが、他の選択肢も検討が進められています。
類洞と呼ばれる肝臓の毛細血管が傷つき、血栓による血流障害がおこることで、肝細胞が壊死してしまう合併症です。通常、移植後約3週間以内にあらわれますが、それ以降にあらわれる遅発性のものもあります。移植前処置の大量化学療法や放射線照射、免疫抑制薬の使用、生着による影響が原因と考えられています。
発症すると、肝臓の腫れやみぞおちの右側辺りの痛み、黄疸があらわれ、腹水が貯まることで体重が増加します。症状は急速にあらわれることがあり、重症化すると心臓や腎臓、呼吸器にも影響を及ぼして多臓器不全になる可能性もあります。
移植に関連する因子(非血縁、HLA不適合、移植前処置の抗がん剤など)、患者に関連する因子(高齢、全身状態など)、肝臓に関連する因子(肝機能障害、肝臓の病気、肝機能障害をきたしやすい薬剤の使用歴など)、小児特有の因子といったリスク因子が特定されており、移植を行う前から医師がリスク因子を評価します。リスクが高い場合は移植前処置で使用する抗がん剤や投与量を調整したり、放射線照射量を調整したりします。治療にはVOD/SOSの治療薬を使用しますが、重症化すると、透析や人工呼吸器が必要になることもあります。
国立がん研究センター:がん情報サービス(2024年5月1日アクセス)
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/hsct03.html
一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(2024年5月1日アクセス)
https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=23
https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=24