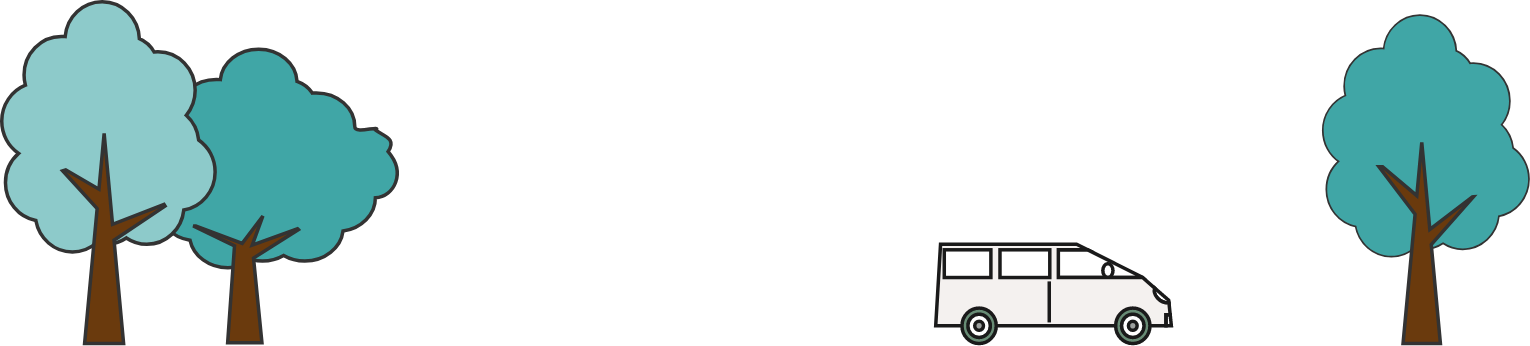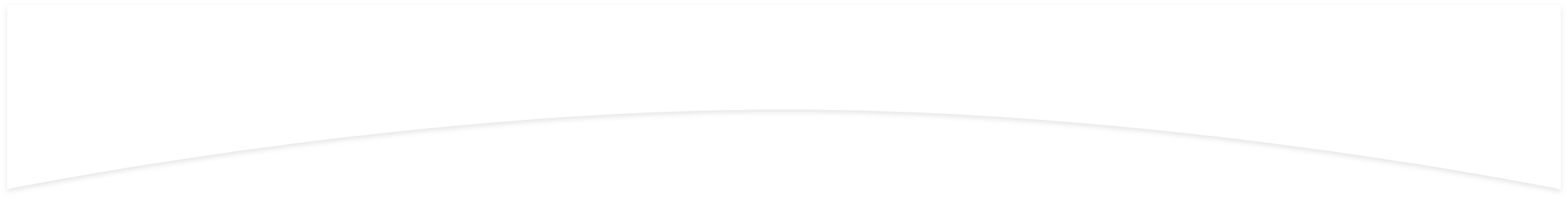

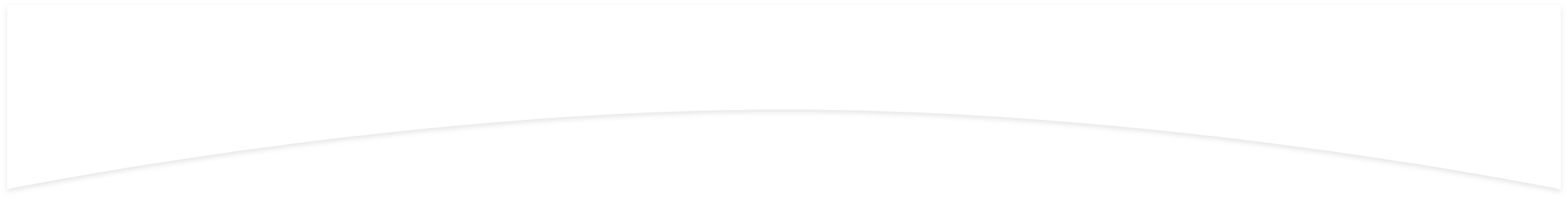

これから移植を受ける患者さんの中には、既に病気休職などの手続きを行った、または既に前職を退職した方もいらっしゃるかもしれません。復職や再就職に向けては、移植を終えて外来受診を続けながら、症状や体調、服薬などについて医師や看護師とも相談しながら、準備を進めていくことになります。
就職や復職、再就職に関しても、全国の「がん相談支援センター」でも相談ができます(「がん相談支援センター」についてはこちら)。
また、厚生労働省では長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)として、全国のハローワークからがん診療連携病院等へ職業相談・職業紹介に応じられるよう出張相談を実施しています。専門相談員の配置ハローワークについては下記一覧をご参照ください。
厚生労働省 「長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065173.html
仕事と治療を両立していくには職場の理解や配慮が不可欠です。復職を目指すにあたって、職場の理解や配慮を得るために、現在の症状や健康状態について医師、看護師やソーシャルワーカーと話し合い、職場に協力をお願いしたいことを整理してみましょう。
職場関係者や上司へ移植後の経過報告をするとともに、仕事内容や職場環境などの制限について話し合いを行いましょう。職場には安全配慮義務があり、必要な場合には就業上の配慮を行う責任がありますが、職場の状況にも理解を示しつつ、必要に応じて医師やがん相談支援センターのスタッフとも連携を取りながら、スムーズに職場復帰できるように準備をしましょう。
職場によっては、復職時に診断書などの提出を求められることがあります。どのような書類が必要になるのか、前もって職場に確認しておきましょう。診断書には、職場にご自身の状況を納得してもらえるよう、どのような働き方が望ましいか、どのような制限を設けたほうがよいかなどの内容を加えてもらうとよいでしょう。
診断書の記載については、厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に様式例がありますので、参考にしてみるのもよいでしょう。
厚生労働省 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
自宅から職場までの通勤については、移植後の体力や感染予防なども考慮して検討します。具体的には、公共の交通機関を利用する場合、混雑時間帯を避けて通勤するなどの工夫が必要になります。職場関係者や上司と相談しながら、ご自身の状態にあわせて無理なく通勤できる方法を考えましょう。通勤の負担が軽減されるリモートワークなども、前もって職場との合意を得ておくとよいかもしれません。
復職直後は、勤務時間を短縮したり、1週間の中の勤務日数を少なくしたりするなどの配慮を得て、その後、徐々に勤務時間や日数を増やしてフルタイム勤務に移行していく、などの措置をとれる場合があります。どのような配慮を得られるかは、職場ときちんと話し合い、調整しましょう。
自分のペースでの仕事を取り戻すには時間がかかるものです。「職場に迷惑をかけたくない」、「以前では普通にできていたことができなくなっている」などと焦りや不安を感じてしまうこともあるでしょう。このようなときには、身体への負担を軽減するのと同じように、心の負担も軽減できるようにすることも大切です。
ひとりで悩む必要はありません。必要に応じて、がん相談支援センターのスタッフに相談したり、同じ経験をしたことのある患者さんの集まりに参加して体験を共有したりすることで、心が楽になることもあるでしょう。
一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会 復職就労支援(2025年3月15日アクセス)
https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=31
厚生労働省 雇用・労働 治療と仕事の両立について(2025年3月15日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
小児の患者さんの場合、学習の遅れを心配することがあるかもしれません。病院によっては、入院して治療が必要な子どもの教育を継続して行うための学級を開設したり、特別支援学校の分校・分教室を併設したりしている場合があります。
就学や復学に関しても、全国の「がん相談支援センター」でも相談ができます(「がん相談支援センター」についてはこちら)。
病院内に併設されている学校のことを、一般的に院内学級と呼びます。院内学級に通うには転校の手続きをする必要がありますが、治療や入院による欠席日数を減らすことができる、ベッドサイドでの学習のため身体負担を軽減して学習ができるといったメリットがあります。また、院内学級は1つの学級に異なる学年の児童が在籍していることもあり、学年を超えての交流もできます。また、同じような境遇にある他の児童と接することで、自身の闘病意欲向上にもつながることがあります。場合によっては入学・卒業時に学校の籍を一時的に地元の学校に戻すことも可能ですので、地元の友達と一緒に入学・卒業を迎えることもできます。一度、地元の学校に相談してみてもよいかもしれません。
私立学校から転校する場合には注意が必要です。私立学校は転校するイコール退学となってしまうため、退院後に復学できるのか、復学可能な場合にはどのようなタイミングで可能なのか、通っていない間の授業料や積立金はどうなるのかなどをきちんと話し合っておきましょう。
現在では、多様なメディアを利用して授業を行うことができるようになりました。病室のICT(情報通信技術)環境が整っていて、在籍中の学校の協力を得ることができれば、病室にいながらにして在籍している学校の授業を同時双方向またはオンデマンドで受けることが可能になります。
治療開始前に通っていた地元の学校に戻りたいといった希望がある場合には、治療中や入院中にもつながりを維持しておくことが大切になります。それにより、治療中の児童の帰る場所を作っておくことができ、孤独感などを軽減できる可能性があります。退院の目途が立ったら、早めに復学の意思・時期を学校側にも伝え、準備を進めることをお勧めします。そうすることで、学校側も教員枠の調整などの受け入れ準備をする時間が確保でき、スムーズな復学につながります。
復学の準備にあたっては、送り迎えなどのご家庭でできるサポート体制や、子どもの体力の回復状況や服薬状況を考慮して復学計画を立てます。特に学校でのサポートが必要な場合には、保護者、学校の先生はもちろんのこと、主治医も交えて、具体的にどのようなサポートが必要かについて話し合うことも大切です。このような機会を持つことで、復学に際しての子どもや保護者の心配・不安を軽減することができ、さらに学校の先生にとっても受け入れの不安を軽減できるよい機会となります。
復学直後は体力の低下などもあり、在学時間を短縮するなどの配慮が必要になるかもしれません。また、外見が気になったり、友達や周囲に病気の理解がなかったり、自分の思いや状態をうまく伝えられないなど、ストレスがかかってしまうこともあるでしょう。身体への負担を軽減するのと同じように、心の負担も軽減できるようなサポートが得られるように環境を整えることも大切です。
復学を考える段階になったら、現在の症状や健康状態について医師、看護師やソーシャルワーカーと話し合い、学校に協力をお願いしたいことを整理してみましょう。
国立がん研究センター:がん情報サービス 小児の方へ がんと学校(2025年3月15日アクセス)
https://ganjoho.jp/public/life_stage/child/school/index.html
国立がん研究センター:がん情報サービス 小児の方へ がんの子どもの療養 復学について(2025年3月15日アクセス)
https://ganjoho.jp/public/life_stage/child/follow_up/aftercare.html
一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(2025年3月15日アクセス)
https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=32