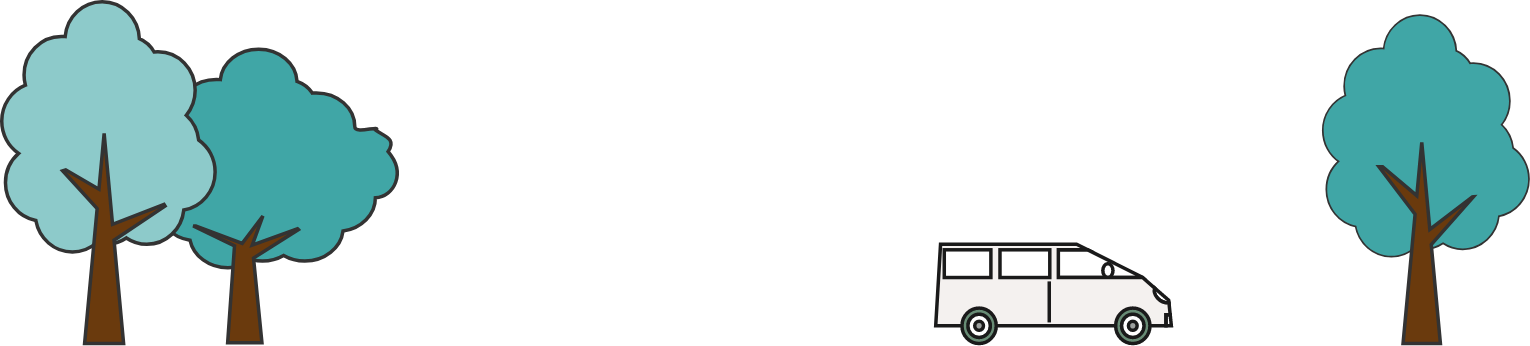プロフィール
木崎 俊明さん大阪大学大学院生。2020年4月に自覚症状を認め、急性骨髄性白血病と診断、抗がん剤治療を開始。2020年9月に同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を実施した。 抗がん剤治療の副作用やGVHD(移植片対宿主病)に悩まされたが、現在は寛解。免疫抑制剤などによる副作用の不安と闘いながら、がんの経験をいかした活動などに取り組んでいる。
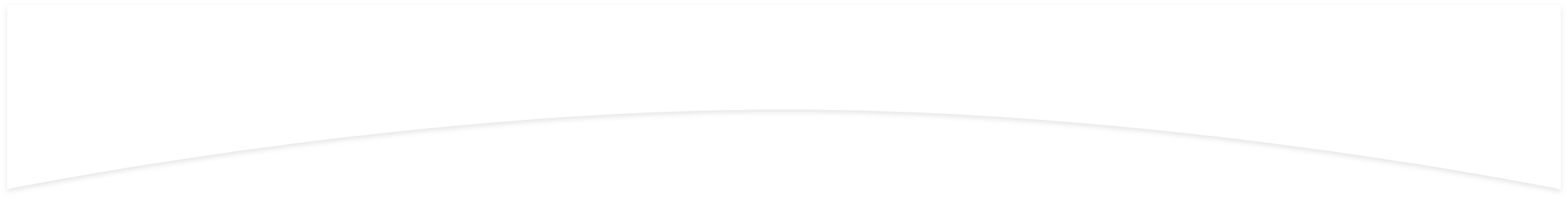


大阪大学大学院生。2020年4月に自覚症状を認め、急性骨髄性白血病と診断、抗がん剤治療を開始。2020年9月に同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を実施した。 抗がん剤治療の副作用やGVHD(移植片対宿主病)に悩まされたが、現在は寛解。免疫抑制剤などによる副作用の不安と闘いながら、がんの経験をいかした活動などに取り組んでいる。
大学院に入学したばかりの2020年4月頃、40度近い高熱が1週間ほど続き、自宅で倒れてしまいました。救急搬送された病院で白血球の数値の異常を指摘され、紹介先の大学病院で急性骨髄性白血病の診断を受けました。
診断時は白血病についての知識がなく、病気の重大さを理解できていなかったと思います。入院時、医師から抗がん剤治療についての説明を受け、合併症や副作用について理解しました。そのとき初めて、白血病の治療の厳しさを痛感し、かなり落ち込みました。両親は私の前では普通に接してくれていましたが、見えないところで泣いていたと後になって妹から聞きました。
白血病と診断された後すぐに、寛解導入療法として抗がん剤治療を1クール、地固め療法として2クール行いました。抗がん剤の副作用は食欲不振と吐き気が特にひどく、病院食を1週間以上食べられない時期もありました。3ヵ月で体重が15キロ以上落ちたことがとてもつらかったです。
抗がん剤治療ののちドナーが見つかり、2020年9月に同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を受けました。末梢血幹細胞移植を受けると決めた大きな理由は、私の白血病は予後が悪く、抗がん剤治療だけでは再発の可能性が高いと医師から聞いていたからでした。
ただ、医師からの治療の説明用紙には治療後の5年生存率や、二次がんの発症リスクの増加などの記載があり、「本当にこの治療にかけてよいのか」という迷いがあったのが本音です。
しかし、再発すればつらい抗がん剤治療をもう一度受けなければならない、移植をすればもう抗がん剤治療をしなくて済むかもしれないという思いから、移植を決めました。
移植前処置である骨髄破壊的処置は、複数の抗がん剤に加えて全身の放射線治療を行ったため、非常につらかったのを覚えています。少しでも治療を楽に進めるため、医療用麻薬も使用し、つらい記憶は比較的少なく済んだと思っています。
移植後、生着するまでの期間は治療の中で最もつらかったです。移植自体は点滴と同じような感じで、あっけなく終わりました。
移植から生着までの間は口や喉の粘膜がただれて痛みが生じ、食事はおろか、唾を飲み込むことさえできませんでした。そのため、ベッドサイドに吸引器を置いてもらい、出てくる唾を飲み込まずに吸引していました。内服薬も錠剤のままでは飲めず、粉状にしてもらい内服していました。
※全ての薬剤が粉砕できるわけではありません。
多くの苦痛があった代わりに、生着したときはとても感動しました。白血病と診断されてからずっと、レールが続くか分からないジェットコースターに乗っているような感覚でした。しかし、生着したときには「あぁ、まだレールは続く可能性があるんだ」とホッとしたのを覚えています。
医師からは移植前にGVHD(移植片対宿主病)について説明を受けました。急性GVHDでは肝機能障害や皮膚症状、消化器症状などが発現するかもしれないと言われ、慢性GVHDでは、全身のあらゆる臓器に障害が出る可能性があるとのことでした。本音を言うと、「あらゆる臓器って何やねん」と思いました。
実際に、移植後2週間くらいまでに皮膚の発疹や肝機能障害といった急性GVHDの症状が現れ、移植後3ヵ月頃からは皮膚の色素沈着や発汗障害、爪の異常、ドライアイ、口腔内の粘膜炎などの慢性GVHDの症状が現れました。移植後3年を過ぎた現在も免疫抑制剤を使用して症状を緩和させています。
移植後3ヵ月で退院しましたが、その頃はちょうどコロナウイルス感染症が流行していた時期でした。そのため人混みへの外出は控えていましたが、体調が少し落ち着いた時期に趣味であったテニスも再開しました。GVHDの皮疹が体表面に10%ほど生じていましたが、つらいながらも乗り切れていました。

退院後は一刻も早く免疫抑制剤を減らしたいと思っていて、順調に減量できていました。しかし、薬の減量に伴って慢性GVHDの症状が悪化してしまうことにより、減量を中断しなければならず、もどかしさを感じていました。また、全身に症状が出るとのことだったので、「これってGVHDかな?」と疑問に思う症状がいくつもありました。その度に医師に相談するようにしていましたが、何がGVHDによるものか判断が難しい場合があり、「別の疾患になっているのかな」という不安がありました。
その頃、テニスの準備運動中に股関節に痛みを感じ、病院で特発性大腿骨頭壊死症と診断されました。GVHD治療で使用したステロイドが関与しているかもしれないと言われたとき、治療に対して強い憤りを感じてしまいました。その後突発性難聴にも罹患し、医師からストレスのない生活をするよう言われました。しかし、股関節の痛みや皮疹の掻痒感が悪化していた時期だったので、「ストレスがない生活は難しいだろう」と感じ、イライラしていました。
人工股関節置換術ののち、リハビリを経て自分の足で歩けるようになり、移植から3年でようやく大学院にも復学できました。さまざまな悩みはもちろんありましたが、自分の足で歩ける喜びはとても大きく、外を散歩できるだけで幸せを感じていました。現在では、私のように移植が終わってもつらい症状に悩まされている人が多いことをたくさんの方に知ってほしいと思っています。
入院中に家族が差し入れをしてくれたことは本当に助かりました。病院食が食べられない時期もあったので、自分が食べたいお菓子を持ってきてくれたのはとてもありがたかったです。サプライズで友人が面会に来てくれたこともありました。コロナウイルス感染症の影響で面会禁止だったので病室に入ってもらうことはできなかったのですが、窓の外から手を振ってくれて、とても嬉しかったのを覚えています。
一方で、周りの方から「大丈夫?」と聞かれることはつらかったです。内心では「大丈夫なわけがない」と思ってしまいますが、心配をかけたくないので無難な回答をしていました。心配してくれているのに、素直に感謝できない自分を責めてしまう時期もありました。他の患者さんにもよくあることかもしれません。私自身、患者さんに声をかけるときは気をつけようと思っています。
また、SNSで友人の楽しそうな写真を見ると、「なぜ自分だけがこんな状況にいるのか」と思ってしまうこともありました。臨床心理士さんや看護師さんを中心に、主治医や研修医の先生に悩みを話したり、泣いたりしていました。アドバイスをもらうというよりは話を聞いてもらうのが中心でしたが、気持ちがスッキリするので私にはよかったですね。
さらに、過去に白血病を経験された看護師さんが病棟にいらっしゃったのもとても心強かったです。同じ病気を克服した人が元気に働いている姿を見て、とても勇気づけられました。
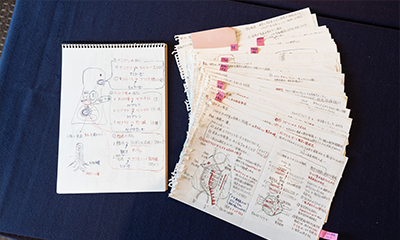
あの頃の自分や、治療に悩んでいる方に出会ったら、医療について知識をつけることを勧めるかもしれません。病気や治療について理解することで、自分の状況をより正確に受け入れられるようになると思います。
「どうしてこの治療ができないんだろう」「この検査の意味は何だろう」と疑問に思ったときは、本やインターネットで調べるようにしていました。また、情報収集の際には、病院や学会などが配信しているWebページなどの信頼できる情報源を選ぶのが重要です。
ときには医師から参考書を借りたり、母に図書館で本を借りてきてもらったりして読むこともありました。病気や治療についてはもちろん、検査データの読み方、新しい治療法につながる論文などさまざまな情報を調べ、その中で気づいたことは医師に伝えるようにしていました。医師の説明も次第に理解できるようになり、自分の置かれた状況を把握できるようになりました。その上で「自分にとって後悔しない選択は何か」について深く考えられるようになりました。また、調べものをするのは入院中の気分転換にもなりました。
白血病になる前は普通の大学生で、もともと工学に興味があり、海外にも関心があったので、「海外に駐在しながら日本のものづくりを世界に広げたい」という夢がありました。白血病を経験した今は、「いつ何があるかわからないから、今やりたいことをやっておこう」と強く思っています。また、医療に貢献していきたいと思うようになり、大学院でも医療に関する勉強をするようになりました。
また、自分の白血病の闘病経験をいかした情報の発信などにも取り組んでいきたいです。白血病や移植についてももちろんですが、移植が終わっても、GVHDに苦しんでいる人が声を上げたり、発信したりすることで、移植後の生活についての理解が深まり、私たちへの見方も変わることにつながるかもしれません。
さらに、「不安や憤りを感じているのは自分だけじゃないんだ」と患者さんが知る機会が増えるのはとても大きな価値があります。すべての患者さんが同じように感じている訳ではありませんが、一人じゃないと分かると少し心が楽になると思います。そういう活動を続けていきたいです。