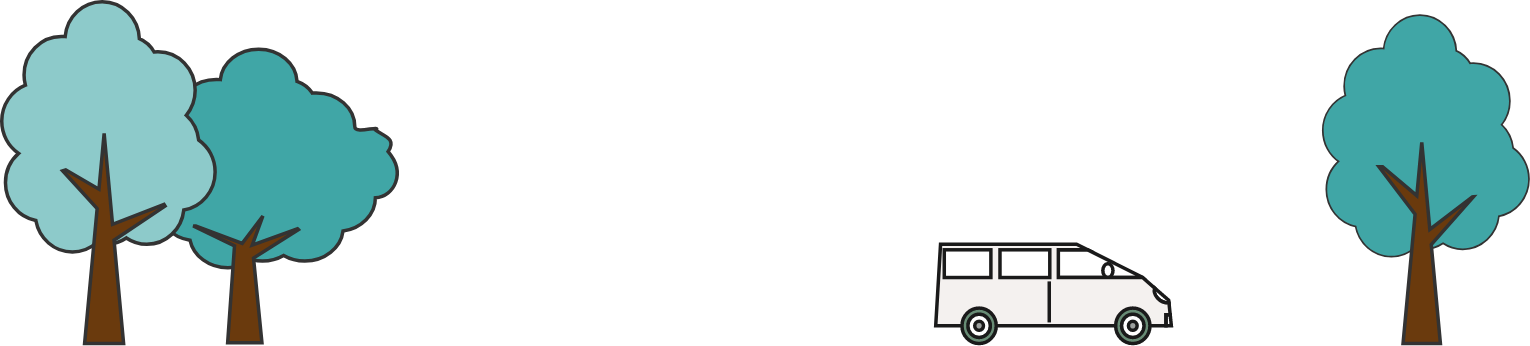プロフィール
後藤 千英さん高校生だった1995年に自覚症状を認め、骨髄異形成症候群と診断を受けた。経過観察を続けていたが、2009年頃から体調が悪化、2012年6月に同種造血幹細胞(骨髄)移植を実施。移植後は皮膚症状や消化器症状などのGVHD(移植片対宿主病)に悩まされた。2013年から社会復帰し、現在は骨髄移植の経験をいかして、語りべとしても活動している。
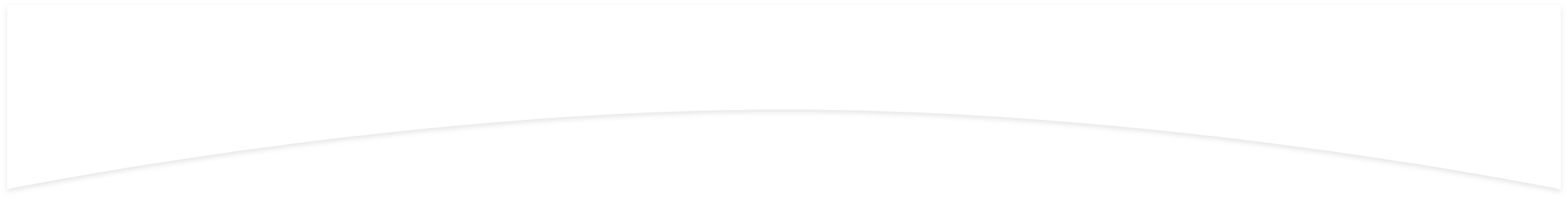


高校生だった1995年に自覚症状を認め、骨髄異形成症候群と診断を受けた。経過観察を続けていたが、2009年頃から体調が悪化、2012年6月に同種造血幹細胞(骨髄)移植を実施。移植後は皮膚症状や消化器症状などのGVHD(移植片対宿主病)に悩まされた。2013年から社会復帰し、現在は骨髄移植の経験をいかして、語りべとしても活動している。
最初に症状に気づいたのは17歳の頃で、突然手の甲が腫れてしまったのがきっかけでした。当時バスケットボール部で活動していたので、ぶつけて怪我でもしたのかと思い、整形外科を受診しました。そこでの血液検査の結果から血液内科の受診を勧められ、骨髄異形成症候群と診断されました。
年齢が若く、急激に症状が悪化する可能性もあることから、入院を勧められました。前日まで普通に生活していた私にとって、まさに青天の霹靂でした。また、インターハイを目指していた時期だったので、自分だけ抜けることはできないと思っていました。しかし、運動をやめるよう医師から伝えられ、病気への恐怖よりも学生生活への不安が募ったのを覚えています。
骨髄異形成症候群は発症しても、症状が悪化しない限り、薬も治療法もありません。私の場合、運良くそこから急激に症状が悪化することはなく、経過観察を続けながら社会人になりました。運動が好きで、友人と山登りやトレッキングを楽しんでいました。けれど、いつからか疲れやすくなり「最近、何かおかしいな」と感じるようになりました。数分立っているだけで疲れてしまったり、階段を上っただけで息切れしてしまったりするようになり、パッと思い浮かんだのが骨髄異形成症候群の悪化でした。心配をかけたくなくて、母には症状を伝えることができませんでした。
症状の悪化に気づいてすぐに受診をしたところ、主治医から輸血を勧められました。しかし、当時の私は、「輸血は事故や手術のときに使うもの」だと思っていたので、自分が使うのには罪悪感のようなものがあり、何度か断っていたのです。最終的に、医師から「貧血から心不全を起こして、命を落とすこともあるんだよ」と言われ、ハッとして輸血を受けるのを決意しました。29歳で初めて輸血を受けて身体がとても楽になり、それまで私が悩んでいた身体のだるさや頭痛、疲れやすさなどがすべて解決して、「今まで我慢していたのは何だったんだろう」と驚きました。
この頃、主治医から同種造血幹細胞(骨髄)移植も提案されました。輸血も断るような当時の私にとって、移植はもってのほかだと考えていましたが、「兄弟が助けてくれるのであれば、やってみてもよいかな」と思い始めました。しかし検査の結果、兄とも弟とも骨髄の型は一致しませんでした。兄と弟は同じ型だったので、とても悲しかったです。
どうしても移植には前向きにはなれなかったのですが、症状がどんどん悪くなる中で「ちゃんと自分で血液が作れるようになったら、私の身体も元に戻れるかも」と考えるようになりました。さまざまな治療法を模索したのち、2012年1月、骨髄移植を受けることを決断しました。
当時治療を受けていた地元の病院でも移植を受けることはできたのですが、まだ骨髄移植の実績がありませんでした。両親や主治医とよく相談して、大阪の病院にセカンドオピニオンをお願いすることにしました。当時の主治医が、「実施する治療は変わらなくても、実績の多い病院だと看護師や薬剤師などのスタッフから受けられるサポートも手厚いと思う」とアドバイスをくださり、いくつかの病院をピックアップしてくれました。結果的に、母の実家から近く、家族のサポートが受けられるということで大阪の病院で治療することにし、母と一緒にいくつか病院を受診しました。そこで、自分の娘のように親身になって相談にのってくれる先生に出会い、その先生に移植をお願いすることに決めました。先生の経験値がとても高かったこと、いつもは何も言わず私の決断を見守ってくれていた母もその先生のことを勧めてくれたのが決め手でした。
移植を決意してからもずっと不安が募り、前向きな気持ちにはなれなかったのを覚えています。前処置が始まる前日、私は「治療に耐えられる自信が全くない」と主治医に伝えました。しかし先生は、「僕たちは経験と自信があるから大丈夫。後藤さんは何も頑張らなくていいからね。頑張るのは僕たちだから」と力強く言ってくれたのです。私にとってはそれがとても嬉しくて、すごく気が楽になりました。今振り返ってみると、あの瞬間が「治療を頑張ろう」とスイッチが入った瞬間だったと思います。
また、移植が決まってからは卵子凍結も行いました。主治医に不妊治療の専門の先生を紹介してもらって、説明を聞きに行きました。採卵にはさまざまなリスクがあり、無事に凍結まで進めたとしても妊娠できる確率は高くはありません。家族からは心配されましたが、将来子どもを望んでいたので、チャンスをもらえたのはとても嬉しかったです。
採卵前には排卵を誘発するための点滴をしたり、輸血で血小板を増やしたりと計画的に準備を行いました。卵子凍結が行えたのは、準備や治療などはもちろん、救急車での移動も検討するなど、病院間で連携してもらえたおかげだと思っています。
治療を頑張ろうと決意した私ですが、前処置から移植まではとてもつらい経験でした。
いろいろな症状が起きているにもかかわらず、自分では何も対処ができませんでした。どんな態勢でも、何をしていてもずっとつらくて、「1人ぼっちで嵐の中へ裸で放り出されたような気持ち」だったのを覚えています。

さらにGVHD(移植片対宿主病)として、皮膚の症状や消化器症状、肝機能の低下、口腔内の乾燥、ドライアイなどが発現しました。特につらかったのは、皮膚の症状です。全身が真っ赤にただれ、ケロイド状になりました。抗がん剤で髪が抜けてしまっていたこともあり、見た目の変化にとても落ち込みました。せっかく元気になるために移植をしたのに、生きる意味がないとまで思ってしまうほどでした。体調が悪い中で保湿剤を塗るのはとても大変で、医師に絶対に治るといわれなかったのも悲しかったです。免疫抑制剤やステロイドの内服を4年ほど続け、症状は徐々に緩和しました。
そのような中で、移植の実績が多い病院での治療を選んだのはとてもよい選択だったと感じています。特に体調が悪いとき、看護師さんは迅速に対応してくださいました。小さなことにも気がついてくれる医療者の方が多くいたことは、安心感につながったと思います。
つらいGVHDの症状の中で、支えになったのはドナーの存在でした。私のために仕事を休み、痛い思いをして提供してくださった方がいるということは、生きる糧になりました。しかし、ドナーに感謝をしている反面、見た目の変化から「これじゃ外に出られない」と思ってしまう自分にもどかしさも感じていました。
そんなとき、私が頼りにしていたのはオンラインでの他の患者との交流です。若い世代の骨髄異形成症候群は症例が少なく、インターネットや本で調べてみてもあまり詳しい情報がありませんでした。そのような中で、オンラインチャットを通して、同じような病気の患者さんと知り合い、情報交換をしたのはとても役に立ったと思います。
患者本人にしかわからない悩みや症状を共有したり、アドバイスをもらったり、時には、おすすめの帽子やパジャマなどの情報交換もしました。抗がん剤治療を受けた人から、「これくらいで症状がましになってきたよ」と実際の体験談を聞けたことは、私を前向きな気持ちにさせてくれました。同じ病気や治療に悩んでいる人がいるのは心の支えでした。
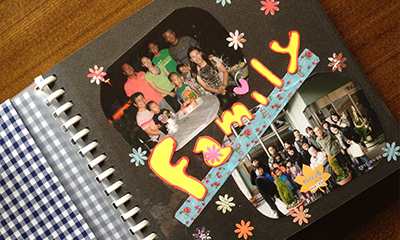
また、家族や友人の支えも大きな励みになりました。面会は家族など特定の人だけで、友人とは会えませんでしたが、メールや手紙をもらったのはとても嬉しかったです。特に印象に残っているのは義姉が作ってくれた、家族との思い出をまとめたアルバムです。地元を離れた入院生活で心細かったのもあり、アルバムは「帰る場所がある」という安心感を与えてくれたと感じています。

私は闘病中、移植を受けて元気になった人に会ってみたいと思っていました。きっと同じように思っている患者さんもいるはずです。私が発信することで、少しでも次の患者さんの参考になればよいと思い、現在は語りべとしての活動や、骨髄バンクの説明員としての活動、卵子凍結の保険適用に向けての働きかけなどにも取り組んでいます。
この取組みを通して、同じ病気になった方から連絡を頂いたり、講演を聞いた方がドナー登録をしてくれたりと、私の想いが伝わったのだと嬉しく思っています。
今振り返ってみると、病気になったことや移植を受けた経験はよい経験になったと思っています。最初は若くして病気になったことを前向きには捉えられませんでした。周囲の人に心配されたり、噂になったりするのも嫌で、病気になったことはなるべく誰にも言わず、隠すべきことのように思っていました。
今、治療を終えたから言えることなのかもしれませんが、たくさんの人に支えてもらい、輸血や移植を通して顔も知らないような方々からも助けてもらって今の私があります。もし私が健康なまま過ごしていたら、きっと骨髄バンクの存在についても知らなかったと思います。そう考えると、よい経験をしたと思いますし、間違いなく私の人生の彩になっていると感じています。
現在闘病中の方は、きっとたくさんの不安があると思います。「絶対に治る」「大丈夫」とは言えないかもしれないけれど、たくさんの患者さんの味方として、支えていける存在になりたいと強く思っています。