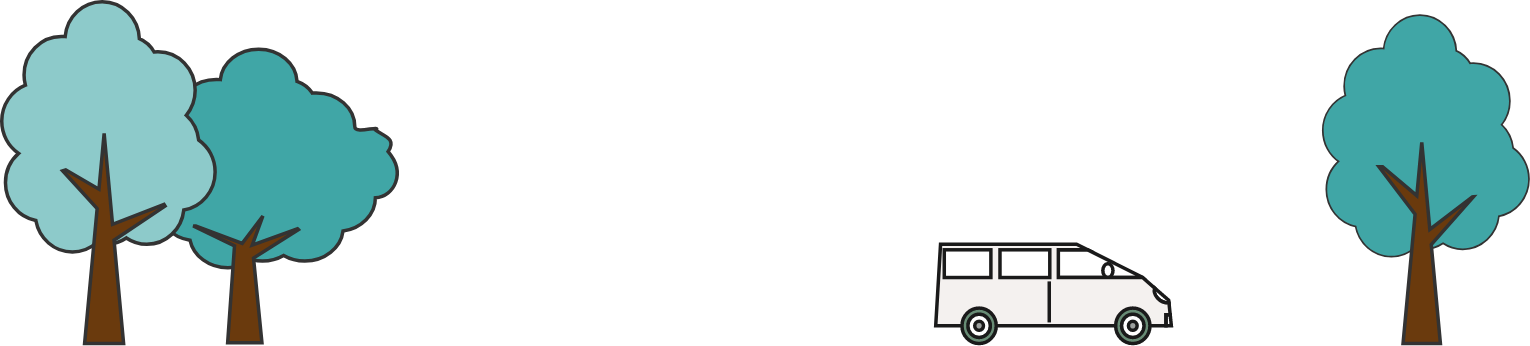プロフィール
角田 雄太郎さん2018年8月頃から腰や胸の痛み、発熱などの体調不良を感じており、翌9月に入院し、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病と診断を受けた。地固め療法を4クール行ったあと、2019年1月に同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を実施。過酷な移植前処置を乗り越え、病気を通じて得た変化を歯科医師である自身の仕事にいかしながら、ポジティブに生活している。
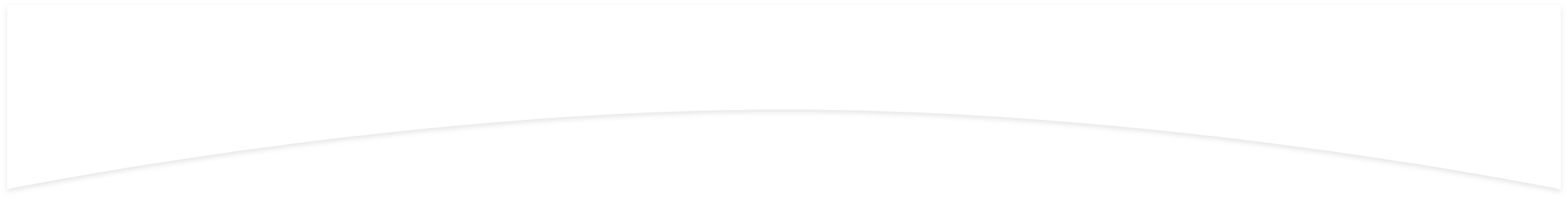


2018年8月頃から腰や胸の痛み、発熱などの体調不良を感じており、翌9月に入院し、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病と診断を受けた。地固め療法を4クール行ったあと、2019年1月に同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を実施。過酷な移植前処置を乗り越え、病気を通じて得た変化を歯科医師である自身の仕事にいかしながら、ポジティブに生活している。

私の実家は、曽祖父が開院した広島の歯科医院で、親子4代にわたり歯科医療を行っています。現在は、父や叔父、弟とともにそこで働いていますが、以前は北九州市におり、将来的には北九州市で開院するつもりでした。しかし、病気をきっかけに人生設計が大きく変わりました。
はっきりと病気が分かったのは、2018年9月です。実はその1カ月くらい前から、発熱やぎっくり腰のような腰の痛み、胸の痛みなど、毎日のように体のどこかに不調を感じていました。しかし、ちょうどその頃仕事がとても忙しく、責任あるポジションを任されていたため、無理をしながらも限界ギリギリまで働いていました。また、子どもが生まれたばかりだったこともあり、喜びとともに「これからもっと頑張らなければ」という気持ちもありました。
最終的には歩けなくなるほど体調が悪化したため、知り合いの先生に相談し採血したところ、自分でもパッと見てすぐに何かの病気だと分かるほど、白血球数、血小板数がよくない数値でした。診察の待ち時間に家族に電話し、「やばいかもしれない」と話したことを覚えています。
その後すぐに入院となり、さまざまな検査を受け、1~2週間後にフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病と診断されました。
「天国から地獄」とは、まさにあのときのことを言うのだなと思います。無事に子どもが生まれ、私の両親にとっては初孫だったこともあり家族中お祝いムード一色でしたが、一転して地獄に突き落とされた感じでした。
また、私の病気が分かる少し前に親しい人が白血病で亡くなっており、自分の現状と重なって落ち込んだり、混乱したり、さまざまな思いが交錯していました。
入院して、地固め療法を4クール実施しました。地固め療法をすると白血球数が減少してしまうため、風邪をひいたり熱を出したり、吐いたりしていて、つらいと言えばつらかったです。味覚が完全になくなった時期もありました。焼きそばを食べたら、匂いはするのに驚くほど味がなく、まるでゴムを食べているような感覚でした。
ただ、移植前処置のつらさは地固め療法のとき以上でした。あまりにもつらくて、全く動けなくなった時期もありました。トイレに行こうとした際、迷走神経反射が起こり、意識を失ったこともあります。
前処置の過酷さから、移植を諦めそうになる人もいるそうですが、「ここまでやって、やめるわけにはいかん!」という気持ちで乗り越えました。
地固め療法が終わり、2019年1月に移植を受けることができたのですが、移植自体はCVC(中心静脈カテーテル)から入っていくだけなので、特にストレスもなく終わりました。
移植後はしばらく体調に波がありつらい日もありましたが、10日目くらいから少しずつ回復してきたと思います。生着自体はほとんど実感がなかったのですが、明らかに体調がよくなっていくのを感じ、うれしかったのを覚えています。
私は、同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植をしましたが、実は移植をしたくないと思っていました。病気のことは自分なりに勉強していましたが、当時は移植による治療成績があまりよくないとも言われていましたし、何より後遺症のようなものが残る可能性があり、元通りの体には戻れないかもしれないという気持ちが強かったからです。また、いずれ治療成績のよい白血病の薬が出て、移植をしなくてもよくなるのではないかという思いもありました。そのため、移植を決心するまでにとても悩みました。最終的には、主治医が自信を持って勧めてくださったことと、「どうしても嫌なら移植しなくてもいい。でも、移植するかしないかは自分で決めなさい」と言われたことで、移植を決断しました。

私には弟が2人いるのですが、ドナーになってくれたのは一番下の弟でした。HLA(ヒト白血球抗原)が完全に一致していなくても移植できると聞きつつ調べてもらったら、なんと弟2人ともフルマッチ(完全一致)だったのです。先生も、そんなことは滅多にないと驚いていました。
HLAの結果が出るまでは弟たちが「どちらかが合うといいな」という話をしてくれていて心強かったのですが、2人とも私と同じだと分かると今度はドナーの譲り合いが始まり、思わず笑ってしまいました。
結局、仕事の都合も考えて三男がドナーになってくれました。治療中、弟が冗談を言って笑わせてくれていたのも、とてもありがたかったです。
GVHD(移植片対宿主病)の急性症状として、ひどい下痢が起こりました。加えて、日焼けのあと薄皮が剥けるように皮膚がカサカサと取れてくるような症状もありました。当時の日記では、「脱皮」と表現していました。また、口腔内の粘膜障害はかなりハードでした。唾液が全く出なくなり、朝起きたら舌と上あごがピタッとくっついて、そのまま舌の表面が剝がれてしまったこともあります。
ただ、先生からは、GVHDは自分の体が戦っている証拠だと言われていたので、症状があってもネガティブには感じませんでした。先生からの前向きな言葉で、とても励まされました。
中には私と年齢が近い先生もいて、色々相談できましたし、親身になってくれました。自分で病気について勉強するための本も買いましたが、先生が最新の治療に関する情報誌を持ってきてくださり、とてもありがたかったです。
私は、病気についてできるだけ知りたいと思っていたし、知識はあったほうがよいと思っていたのでかなり勉強しましたが、知ることで不安になる人もいるようです。私自身、調べていくうちに不安にもなりましたが、最終的には「生きていればどうにかなる!」と思うようになりました。
それでも、精神的なダメージはやはり大きかったです。「なぜ自分なんだろう」と、繰り返し考えていました。お酒もそれほど飲まないし、たばこも吸わない、仕事も一生懸命してきたし、わりとまじめに生きてきたつもりだったのに、なぜ、と落ち込みました。
入院中も、人といるときは割と明るく振る舞い「やるしかないよね」と言っていたのですが、1人になると気持ちが一気に落ち込み、夜に泣いていたこともあります。
そうした中、家族や両親、友人など、色々な人が会いに来てくれたことは、とても励みになりました。特に子どもの存在は大きかったです。顔を見るだけでも元気が出ました。
一方で、周囲の「頑張れ」が、少し重かった時期もありました。
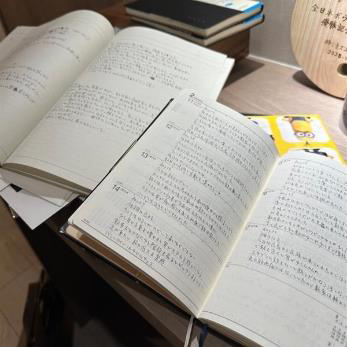
私は、病気が分かった日からずっと日記をつけていたのですが、自分の気持ちを吐き出したり、整理したりするためにも書いてよかったなと思います。それから、SNSにもずいぶんと助けられました。特に無菌室に入ると誰にも会えず、やることがないため、1日がとても長く感じました。SNSに届くコメントへの返信を日課としていたおかげで、1人の時間も何とか乗り切ることができました。
SNSでは、同じような境遇の方の情報を目にすることがあったり、つながりを持ったりすることもありました。その中には、信憑性に欠ける内容や危険だと感じる情報もありました。明らかに間違った情報や根拠のない書き込みも見られたため、治療を続けていく上で正しい情報を収集することが重要だと思います。
現在、「移植をしてよかった」という思いが大半ですが、病気になったことで、住む場所やキャリアプランは大きく変わりました。治療前に住んでいた北九州市は妻の実家があり、私も大好きな場所です。病気が分かり、結果的に地元の広島に戻ることになりましたが、もともと北九州市に骨を埋めるつもりでしたし、「そろそろ開業したい」と真剣に考えている時期でもあったので、病気によって人生が大きく変わってしまったという思いはあります。本来ならもっと早く開業していたはずなのに、と考えてしまう日もあります。しかし、今になってみると開業資金を借りる前に病気が分かってよかったなと思います。
病気を通じて失ったものはいくつかありますが、得たものもあります。一番は、歯科治療に来てくれる患者さんに対する向き合い方の変化です。相手の悩みにもっと寄り添いたいという思いや、理解したいという気持ちはこれまでより厚みが出たのではないかと思います。もちろん、それにより技術力がアップするわけではありませんが、若く健康だったときは分からなかった患者さんの気持ちや、口腔内以外の疾患を持つ患者さんのつらさや状況などにも、より気を配れるようになりました。
これは、病気を経験したからこそ得られた貴重な変化だと思っています。